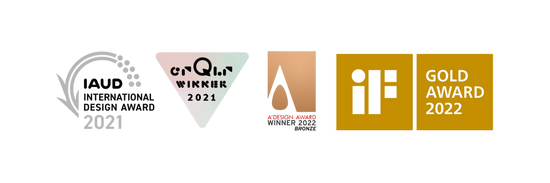Care? Repair? or Send to next user?
For inquiries about repairs or returns of your SOLIT items, please contact us here!
SHORT DOCUMENTARY
-
All Inclusive Society / 多様性の先の世界
This video is a documentary movie of our journey throughout "Vancouver Fashion Week" held in April 2024, and we, SOLIT were invited to participate. We aimed to tackle the challenges of diversity in fashion, from concept to execution, collaborating with a diverse group of people from the planning stages through radical participatory design, and inclusive design.
このビデオは、私たちSOLITが2024年4月に開催された「バンクーバーファッションウィーク」に招待された際のドキュメンタリー映像です。ファッションショーに挑む私たちは、企画段階から多様な人々と協力し、多様なファッションにおける課題をプロダクトとショーの設計全体で解決することを目指しました。これはいわば参加型デザインやインクルーシブデザインの実践でもあり、一種の未来に向けたデモ活動でもあります。 -
SOLIT! A Bright light of hope / SOLIT!明日に差す光
Two years after its founding, SOLIT is on the world stage, winning GOLD, the top award at the iF DESIGN AWARD 2022, one of the world's top three design awards.
iF DESIGN CEO Uwe talks to SOLIT founder Misaki Tanaka as she heads to the awards ceremony in Berlin, Germany, and about the appeal of SOLIT, which was selected from amongst designs from around the world.
創業から2年で世界の舞台に立ったSOLIT。
世界3大デザインアワード「iF DESIGN AWARD 2022」にて、最優秀賞であるGOLDを受賞。全世界からのエントリーで、受賞確率1%未満とされる狭き門に2年で到達してしまう。
ドイツ・ベルリンでの授賞式に向かうSOLIT創業者の田中美咲のその姿と、世界中のデザインの中から選ばれたSOLITの魅力についてiF DESIGNのCEO Uweが語る。
AWARD
NEWS
- 2026.1
- 2024.6.1
-
2024.5.27
Updated information on August try-on events in Shinagawa, Tokyo and Fukui, Japan
- 2024.5.13
- 2024.4.23