JOURNAL

SOLIT吸収合併に寄せて / 執筆 代表 田中美咲
WEBサイトでのお知らせなどを見て、いきなりのご報告で驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。 >> 吸収合併のお知らせ 実は昨年の夏ごろから、チームのみんなとこれからのSOLITはどうあるべきだろうかと議論を重ねてきました。そうした長い議論の中で、フルタイムで働くメンバーから、多様な意見をくれるアドバイザリーボードの皆さん、株主のみなさんをはじめ、いろんな方と話す中で決めたのが今回の吸収合併の決断になります。 最近海外コレクションに出場したばかりじゃないか! こんなにアワードを受賞したり、メディアに取材してもらってるじゃないか! 会社をなくすなんて勿体無い! こんな言葉も、たくさんの方からいただきました。 そう言ってもらえるほど何らかの成果を残し、そして記憶に残る要素を生み出せたと思うととても嬉しいと共に、そうした有難いお言葉をいただいても尚、私の中では「このままではダメだ」という思いが消えませんでした。 「SOLIT」という人格を宿す法人格は、とても正義感が強く、凛として、挑戦を止めず、世間一般でいう「良い」とは時に距離を置いてまでも、自分達の倫理観による「良い」を定め、可能性の範囲を決めずに挑戦をおこなってきました。SOLITに関わる人や、SOLIT自身はとても潔くてかっこいいと、創業者ながらに感じています。 だからこそ、初志貫徹、創業時の思いをブラさずに「ファッションから始めるけれど、それはあくまで前例を作るためであり、本来やるべきは多様な人や地球環境も考慮されたオールインクルーシブな社会を作ること」にちゃんと立ち戻りたいと、そう思いました。 ファッションは第一弾であり、ここからはたくさんの人と手を組んで実現させる 私たちは創業時から、「SOLIT!」というインクルーシブデザイン×ファッションでの前例をつくり、いわゆるショーケースを生み出すことで轍を作り、次にその開発において蓄積させたエビデンスやデータや知見をまとめ、最後に多分野の企業や団体と連携しながら、人間が暮らす上で必要な分野・要素において「オールインクルーシブ」な選択肢を増やしていき、人モノ金が循環するシステムを加速させて経済圏をつくっていきたい、そう考えていました。 まずはファッションでは、 プロダクトのデザインにこだわり 生産背景とサプライチェーンにおける環境/人権にこだわり 国内外からデザイン/ファッションとして評価を受け ファッションコレクションでそれらを多くの人に提示しにいく といった、前例を作る上で必要な要素はまとまったと思っています。 もちろん、まだまだ解決すべきことは山ほどあります。届いていない人たちもたくさんいる。けれど、創業時と比べて多くのプレイヤーが参入してくださったことで、大きな解決の流れは既に生まれ始めています。そうすると、「私たちでなくてはならない」ということはもう過ぎたのかなと思っています。 ここからは、既にコクヨやPanasonic FUTURE LIFE FACTORY、アイシンの皆さんともご一緒していますが、ファッションにとどまらない分野で選択肢を増やしていくことに力を入れ、多くの企業や団体、個人の方とご一緒していきたいと思っています。 まさに、「仲間を集め、仲間と手を組む」フェーズに入ったのです。 その魂を宿す「身体」を変える SOLITは、魂は残るけれど、その魂を宿す「身体」を変えます。 代表である私がもう一つ経営をしている、社会課題解決に特化した企画・PRの会社「morning after cutting...
SOLIT吸収合併に寄せて / 執筆 代表 田中美咲
WEBサイトでのお知らせなどを見て、いきなりのご報告で驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。 >> 吸収合併のお知らせ 実は昨年の夏ごろから、チームのみんなとこれからのSOLITはどうあるべきだろうかと議論を重ねてきました。そうした長い議論の中で、フルタイムで働くメンバーから、多様な意見をくれるアドバイザリーボードの皆さん、株主のみなさんをはじめ、いろんな方と話す中で決めたのが今回の吸収合併の決断になります。 最近海外コレクションに出場したばかりじゃないか! こんなにアワードを受賞したり、メディアに取材してもらってるじゃないか! 会社をなくすなんて勿体無い! こんな言葉も、たくさんの方からいただきました。 そう言ってもらえるほど何らかの成果を残し、そして記憶に残る要素を生み出せたと思うととても嬉しいと共に、そうした有難いお言葉をいただいても尚、私の中では「このままではダメだ」という思いが消えませんでした。 「SOLIT」という人格を宿す法人格は、とても正義感が強く、凛として、挑戦を止めず、世間一般でいう「良い」とは時に距離を置いてまでも、自分達の倫理観による「良い」を定め、可能性の範囲を決めずに挑戦をおこなってきました。SOLITに関わる人や、SOLIT自身はとても潔くてかっこいいと、創業者ながらに感じています。 だからこそ、初志貫徹、創業時の思いをブラさずに「ファッションから始めるけれど、それはあくまで前例を作るためであり、本来やるべきは多様な人や地球環境も考慮されたオールインクルーシブな社会を作ること」にちゃんと立ち戻りたいと、そう思いました。 ファッションは第一弾であり、ここからはたくさんの人と手を組んで実現させる 私たちは創業時から、「SOLIT!」というインクルーシブデザイン×ファッションでの前例をつくり、いわゆるショーケースを生み出すことで轍を作り、次にその開発において蓄積させたエビデンスやデータや知見をまとめ、最後に多分野の企業や団体と連携しながら、人間が暮らす上で必要な分野・要素において「オールインクルーシブ」な選択肢を増やしていき、人モノ金が循環するシステムを加速させて経済圏をつくっていきたい、そう考えていました。 まずはファッションでは、 プロダクトのデザインにこだわり 生産背景とサプライチェーンにおける環境/人権にこだわり 国内外からデザイン/ファッションとして評価を受け ファッションコレクションでそれらを多くの人に提示しにいく といった、前例を作る上で必要な要素はまとまったと思っています。 もちろん、まだまだ解決すべきことは山ほどあります。届いていない人たちもたくさんいる。けれど、創業時と比べて多くのプレイヤーが参入してくださったことで、大きな解決の流れは既に生まれ始めています。そうすると、「私たちでなくてはならない」ということはもう過ぎたのかなと思っています。 ここからは、既にコクヨやPanasonic FUTURE LIFE FACTORY、アイシンの皆さんともご一緒していますが、ファッションにとどまらない分野で選択肢を増やしていくことに力を入れ、多くの企業や団体、個人の方とご一緒していきたいと思っています。 まさに、「仲間を集め、仲間と手を組む」フェーズに入ったのです。 その魂を宿す「身体」を変える SOLITは、魂は残るけれど、その魂を宿す「身体」を変えます。 代表である私がもう一つ経営をしている、社会課題解決に特化した企画・PRの会社「morning after cutting...

不定期・期間限定販売に切り替えます
2024年4月、バンクーバーでのファッションショーを経て、チームで何度も議論をし、私たちはやっぱり「ただ服をたくさん売りたいわけではない」ということを再確認しました。だからこそ、自分達の正義感や倫理観といった形のない大切にしたいことに対して誠実に、そして創業時からの実現したい未来にむけて、私たちが選びたい選択肢を取りに行くことに決めました。 販売を、もっとゆっくり行うことにしました。 すでにSOLIT!では在庫を持たないことによって廃棄を生み出さないよう、受注生産もしくは最小ロットでの生産を続けてきています。これによって、オーダーしてくださった方には45日程度お待ちいただきながらも、1つ1つ丁寧に制作をしてお届けすることができています。 これまでも、私たちは常に当たり前や前例をただ踏襲するのではなく、「多様な人も地球環境も考慮された未来を作るためにどうすべきか」を検討しては改善を繰り返してきました。 そんな中で、ある時、私たちの商品が大手フリマサイトで販売されているのを発見しました。衣類の多くは、袖を通されなくなった後は「燃えるゴミ」の中に捨てられてしまうことが多いので、再販してまでも購入される価値があると考えてくださっているという喜びのような気持ちが生まれたことも事実です。 しかし同時に、購入してくださった方の手元にある寿命が短かったのだと捉え直すと、私たちが作ったものがたくさんの方に手に取ってもらえたとしても、手に取ったことでその人のなんらかの課題が解決されていたとしても、短い期間で手元を離れてしまうなら、地球環境にとってはどうなのだろうかと、ジレンマも抱えることになりました。例え人間にとっての課題解決になっていたとしても、私たちSOLITが目指す世界に対して、地球環境が置き去りになってしまうのはやっぱり違うなと感じたのです。 いつでも買える状態は消費を加速させてしまってる? 大量生産大量消費大量廃棄に加担をしたくないけれど、必要な人に必要なものを必要な分だけお届けしたい こんな想いを抱えながらも、「『いつでも買える』が消費を加速させるのではないか?」という問いが私たちの頭を駆け巡っていきます。そして、そもそも私たちは「どうしても欲しい」と思ってもらえているものを作れているのかという疑問も抱くきっかけになりました。 元々受注生産という仕組みを選んでいる以上、必要としていただいている方に届く構造にはなっていると思いつつ、そこをより研ぎ澄ましていくことで、「どうしても欲しいものは常に目の前にある必要はないのではないか」、「どうしても欲しい・必要だと思ってもらえるものを作ることで、もっと長く大切にしてもらえることに繋がっていくのではないか」という仮説のような考えに辿り着いたのです。 長く大切につかってもらうために 私たちはこれからは、製造のスピードを落とし、購入ができる機会を減らし、購入ができる機会を減らし、その分長く大切に使ってもらえるものを作ろうと考えています。もっと長く使ってもらえるものを作ろうと考えています。 1)どうしても欲しいと思ってもらえるプロダクトのみをつくる2)販売期間を限定し、待ち望んでもらえる環境を作る3)手に入れられる機会を限定することで、今既に存在するものをリペアして使い続ける環境を生み出したり、大切に使ってもらえるような環境を作っていく 全ての消費を止めるべきだと考えているのではありません。ただ目の前にある服やそこに対する想いを大切にしていきたいと思うその気持ちを、仕組みという形から生み出してみたいのです。 5月17日(金)から5月26日(日)まで まずは今回、バンクーバーファッションコレクションに出場した際に新たに生み出したデザインのアイテムは、5月17日(金)から5月26日(日)という期間限定で販売をいたします。そしてその他の衣服に関しても、できるだけ対面で対話をしながらオーダーいただく機会をつくるか、事前告知のもとで不定期の販売期間を設ける形に切り替えていきたいと思います。 半年後にある誕生日を楽しみにするように、1年後に見れる映画の予告を見るように、4年後に迫る国際大会を楽しみにするように。時には、10年後に見られるタイムカプセルに願いをこめる時のように。 「待つ」ことすらも、地球のためや生産に携わる全ての人のためであると捉え直せたら。そう期待して、新たなチャレンジを始めてみようと思います。
不定期・期間限定販売に切り替えます
2024年4月、バンクーバーでのファッションショーを経て、チームで何度も議論をし、私たちはやっぱり「ただ服をたくさん売りたいわけではない」ということを再確認しました。だからこそ、自分達の正義感や倫理観といった形のない大切にしたいことに対して誠実に、そして創業時からの実現したい未来にむけて、私たちが選びたい選択肢を取りに行くことに決めました。 販売を、もっとゆっくり行うことにしました。 すでにSOLIT!では在庫を持たないことによって廃棄を生み出さないよう、受注生産もしくは最小ロットでの生産を続けてきています。これによって、オーダーしてくださった方には45日程度お待ちいただきながらも、1つ1つ丁寧に制作をしてお届けすることができています。 これまでも、私たちは常に当たり前や前例をただ踏襲するのではなく、「多様な人も地球環境も考慮された未来を作るためにどうすべきか」を検討しては改善を繰り返してきました。 そんな中で、ある時、私たちの商品が大手フリマサイトで販売されているのを発見しました。衣類の多くは、袖を通されなくなった後は「燃えるゴミ」の中に捨てられてしまうことが多いので、再販してまでも購入される価値があると考えてくださっているという喜びのような気持ちが生まれたことも事実です。 しかし同時に、購入してくださった方の手元にある寿命が短かったのだと捉え直すと、私たちが作ったものがたくさんの方に手に取ってもらえたとしても、手に取ったことでその人のなんらかの課題が解決されていたとしても、短い期間で手元を離れてしまうなら、地球環境にとってはどうなのだろうかと、ジレンマも抱えることになりました。例え人間にとっての課題解決になっていたとしても、私たちSOLITが目指す世界に対して、地球環境が置き去りになってしまうのはやっぱり違うなと感じたのです。 いつでも買える状態は消費を加速させてしまってる? 大量生産大量消費大量廃棄に加担をしたくないけれど、必要な人に必要なものを必要な分だけお届けしたい こんな想いを抱えながらも、「『いつでも買える』が消費を加速させるのではないか?」という問いが私たちの頭を駆け巡っていきます。そして、そもそも私たちは「どうしても欲しい」と思ってもらえているものを作れているのかという疑問も抱くきっかけになりました。 元々受注生産という仕組みを選んでいる以上、必要としていただいている方に届く構造にはなっていると思いつつ、そこをより研ぎ澄ましていくことで、「どうしても欲しいものは常に目の前にある必要はないのではないか」、「どうしても欲しい・必要だと思ってもらえるものを作ることで、もっと長く大切にしてもらえることに繋がっていくのではないか」という仮説のような考えに辿り着いたのです。 長く大切につかってもらうために 私たちはこれからは、製造のスピードを落とし、購入ができる機会を減らし、購入ができる機会を減らし、その分長く大切に使ってもらえるものを作ろうと考えています。もっと長く使ってもらえるものを作ろうと考えています。 1)どうしても欲しいと思ってもらえるプロダクトのみをつくる2)販売期間を限定し、待ち望んでもらえる環境を作る3)手に入れられる機会を限定することで、今既に存在するものをリペアして使い続ける環境を生み出したり、大切に使ってもらえるような環境を作っていく 全ての消費を止めるべきだと考えているのではありません。ただ目の前にある服やそこに対する想いを大切にしていきたいと思うその気持ちを、仕組みという形から生み出してみたいのです。 5月17日(金)から5月26日(日)まで まずは今回、バンクーバーファッションコレクションに出場した際に新たに生み出したデザインのアイテムは、5月17日(金)から5月26日(日)という期間限定で販売をいたします。そしてその他の衣服に関しても、できるだけ対面で対話をしながらオーダーいただく機会をつくるか、事前告知のもとで不定期の販売期間を設ける形に切り替えていきたいと思います。 半年後にある誕生日を楽しみにするように、1年後に見れる映画の予告を見るように、4年後に迫る国際大会を楽しみにするように。時には、10年後に見られるタイムカプセルに願いをこめる時のように。 「待つ」ことすらも、地球のためや生産に携わる全ての人のためであると捉え直せたら。そう期待して、新たなチャレンジを始めてみようと思います。
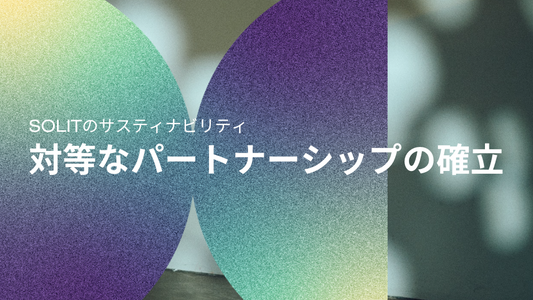
対等なパートナーシップの確立
私たちPROJECT SOLITが大切にしているサスティナビリティの視点のひとつ、「対等なパートナーシップの確立」についてご紹介します。 関連記事:SOLITの5つのサステナビリティ 対等なパートナーシップの確立 現行の大量生産を請け負う生産工場の多くは、付属品の指定や販売価格が既に決定しており、そこから縫製する価格を算出し請け負うため、生産工場で縫製のしやすさ、請け負う価格などの検討の余地がないことが多くなっています。 しかし、SOLITでは、作り手と一緒に「作り方から相談」して決めていくことを大切にしようと考え、生産のパートナーとして対等な議論を交わすことのできる関係構築を重視しています。 「余白」を残した依頼 決め切ったものを依頼するのではなく、作り手とチームになって一緒に考える「余白」を残した依頼を可能にすることで、縫製担当者の不必要な縫製を削減でき、時にデザインの改善や他の選択肢をともに考え、生み出せるような関係性を作っています。 Code of conduct そのために、Code of conductを取り交わし、SOLITが大切にしたい環境や人権への配慮について事前に共有した上で理解と共感をいただいた先と連携することを決めています。Code of conductで約束する行動指針に関しては、お互いに対等に責任が発生するため、私たちだけではなく生産工場の環境改善や人権保護にも寄与でき、お互いに対話を続けて改善していくことができるような仕組みを作っています。 また、多様な人が着やすい服を作るための生産にはとても手間が掛かります。私たちは、作り手の方々にも敬意をこめて、チームとして一緒に考える余白を残すこと、適正な対価を支払うことで、対等なパートナーシップを確立してきました。
対等なパートナーシップの確立
私たちPROJECT SOLITが大切にしているサスティナビリティの視点のひとつ、「対等なパートナーシップの確立」についてご紹介します。 関連記事:SOLITの5つのサステナビリティ 対等なパートナーシップの確立 現行の大量生産を請け負う生産工場の多くは、付属品の指定や販売価格が既に決定しており、そこから縫製する価格を算出し請け負うため、生産工場で縫製のしやすさ、請け負う価格などの検討の余地がないことが多くなっています。 しかし、SOLITでは、作り手と一緒に「作り方から相談」して決めていくことを大切にしようと考え、生産のパートナーとして対等な議論を交わすことのできる関係構築を重視しています。 「余白」を残した依頼 決め切ったものを依頼するのではなく、作り手とチームになって一緒に考える「余白」を残した依頼を可能にすることで、縫製担当者の不必要な縫製を削減でき、時にデザインの改善や他の選択肢をともに考え、生み出せるような関係性を作っています。 Code of conduct そのために、Code of conductを取り交わし、SOLITが大切にしたい環境や人権への配慮について事前に共有した上で理解と共感をいただいた先と連携することを決めています。Code of conductで約束する行動指針に関しては、お互いに対等に責任が発生するため、私たちだけではなく生産工場の環境改善や人権保護にも寄与でき、お互いに対話を続けて改善していくことができるような仕組みを作っています。 また、多様な人が着やすい服を作るための生産にはとても手間が掛かります。私たちは、作り手の方々にも敬意をこめて、チームとして一緒に考える余白を残すこと、適正な対価を支払うことで、対等なパートナーシップを確立してきました。

生み出し方と生み出す責任
私たちPROJECT SOLITが大切にしているサスティナビリティの視点のひとつ、「私たちの生み出し方と生み出す責任」についてご紹介します。 関連記事:SOLITの5つのサステナビリティ SOLITが大切にしている「生み出し方」 はじまりはすべて誰かの「願い」から SOLITでは、全てのプロダクトについて課題当事者の方にヒアリングを行いながら、プロダクトの修正を繰り返し、製品化に至ります。 1商品あたり、約100名の方にアンケートやヒアリングを実施し、試作品を着用してもらい、さらに修正を加えて... どんなに課題が解決できたプロダクトになったとしても、商品を生むことで生産から循環に至るまで「誰かを傷つけないか」、この形状やアプローチは「価値観の押し付けになっていないか」と、繰り返し議論をすることを大切にしています。 これは、インクルージョンの視点から当たり前に重要なことであると共に、「本当に必要とされるものを生み出す」ということでサステナビリティの観点にもつながっていくポイントだと考えているからです。 「課題当事者の方が本当に嬉しいか」を意思決定の判断軸とする 課題当事者の方の言葉や想いをヒアリングした上で、初めて判断する。本当にこれが「正しい」かどうかは、SOLITメンバーも工場で縫製しているメンバーも判断することができないという事実を常に意識することを忘れないようにしています。 体型や障がいの度合い、好みや価値観や思想も人それぞれな中で、SOLITの製作・検証をはじめとする企画段階では、様々な障害の方、年齢、体型、セクシュアリティの方にとにかくたくさんご着用いただくようにしています。どんなプロダクトだったとしても、製品化されたアイテムの最終決定者は、課題当事者の方々です。 多様な人も、地球環境もインクルードするデザインである SOLITのインクルーシブデザインは、障がい者・高齢者といった「スペシャルニーズ」を持つ人にとどまりません。Human DiverstyからBio Diversityまで、あらゆる存在を包括するために議論をして生み出すことを重視し、問いを投げかけるようにしています。 SOLITが大切にしている「生み出す責任」 必要なものを、必要な人に、必要な分だけ生み出す 不必要なものは生み出さず、環境負荷の軽減をはかっています。必要とされてから必要な分だけ作り出す「完全受注生産」「最少ロット生産」にこだわり、プロダクトの生産をしています。 企画段階からファッションに課題を感じてきた「課題当事者」とともに必要なものだけを開発します。 画一的なデザインの提供ではなく、それぞれの好みや身体の特徴に合わせて、「着る人が選ぶ」を実現するための仕組みを構築しています。 同じ未来の実現に賛同する企業や医療・福祉事業者と連携し、これまでにないプロダクト開発や環境設計など、私たちが持つ知識やデータを活用した企画・伴走支援も行います。 PROJECT SOLITでは、多様な人と地球環境に対して配慮し行動を起こすことは、これからのファッション業界・ものづくりを担う者として「やらないという選択肢はない」と考えています。創業当初から続いたインクルーシブファッションサービス「SOLIT!」に関しては、上記のポイントを守った開発を続けてきました。 もちろん、私たちもまだまだ完璧とはいえませんし、組織の状況やプロジェクトのフェーズなどの事情で取り組むことができる範囲は変わってくるかもしれません。それでも、配慮すべき点や取り組むべきことがまだまだ多くある中で、「今できる形は何だろう」と考えることを諦めず、工夫できる範囲から始めていくことが肝要です。 だからこそ、「やらなければならないから仕方なくやる」というところから抜け出し、「必要だと感じるから工夫を続ける」ところに至ることも大切だと考えています。そのために、思考停止せず、「今私たちにできること」の最大限を積み重ねていくためのお手伝いもさせていただきながら、私たち自身も含め、少しずつサステナブルな未来や世界を実現していくことができればと思っています。
生み出し方と生み出す責任
私たちPROJECT SOLITが大切にしているサスティナビリティの視点のひとつ、「私たちの生み出し方と生み出す責任」についてご紹介します。 関連記事:SOLITの5つのサステナビリティ SOLITが大切にしている「生み出し方」 はじまりはすべて誰かの「願い」から SOLITでは、全てのプロダクトについて課題当事者の方にヒアリングを行いながら、プロダクトの修正を繰り返し、製品化に至ります。 1商品あたり、約100名の方にアンケートやヒアリングを実施し、試作品を着用してもらい、さらに修正を加えて... どんなに課題が解決できたプロダクトになったとしても、商品を生むことで生産から循環に至るまで「誰かを傷つけないか」、この形状やアプローチは「価値観の押し付けになっていないか」と、繰り返し議論をすることを大切にしています。 これは、インクルージョンの視点から当たり前に重要なことであると共に、「本当に必要とされるものを生み出す」ということでサステナビリティの観点にもつながっていくポイントだと考えているからです。 「課題当事者の方が本当に嬉しいか」を意思決定の判断軸とする 課題当事者の方の言葉や想いをヒアリングした上で、初めて判断する。本当にこれが「正しい」かどうかは、SOLITメンバーも工場で縫製しているメンバーも判断することができないという事実を常に意識することを忘れないようにしています。 体型や障がいの度合い、好みや価値観や思想も人それぞれな中で、SOLITの製作・検証をはじめとする企画段階では、様々な障害の方、年齢、体型、セクシュアリティの方にとにかくたくさんご着用いただくようにしています。どんなプロダクトだったとしても、製品化されたアイテムの最終決定者は、課題当事者の方々です。 多様な人も、地球環境もインクルードするデザインである SOLITのインクルーシブデザインは、障がい者・高齢者といった「スペシャルニーズ」を持つ人にとどまりません。Human DiverstyからBio Diversityまで、あらゆる存在を包括するために議論をして生み出すことを重視し、問いを投げかけるようにしています。 SOLITが大切にしている「生み出す責任」 必要なものを、必要な人に、必要な分だけ生み出す 不必要なものは生み出さず、環境負荷の軽減をはかっています。必要とされてから必要な分だけ作り出す「完全受注生産」「最少ロット生産」にこだわり、プロダクトの生産をしています。 企画段階からファッションに課題を感じてきた「課題当事者」とともに必要なものだけを開発します。 画一的なデザインの提供ではなく、それぞれの好みや身体の特徴に合わせて、「着る人が選ぶ」を実現するための仕組みを構築しています。 同じ未来の実現に賛同する企業や医療・福祉事業者と連携し、これまでにないプロダクト開発や環境設計など、私たちが持つ知識やデータを活用した企画・伴走支援も行います。 PROJECT SOLITでは、多様な人と地球環境に対して配慮し行動を起こすことは、これからのファッション業界・ものづくりを担う者として「やらないという選択肢はない」と考えています。創業当初から続いたインクルーシブファッションサービス「SOLIT!」に関しては、上記のポイントを守った開発を続けてきました。 もちろん、私たちもまだまだ完璧とはいえませんし、組織の状況やプロジェクトのフェーズなどの事情で取り組むことができる範囲は変わってくるかもしれません。それでも、配慮すべき点や取り組むべきことがまだまだ多くある中で、「今できる形は何だろう」と考えることを諦めず、工夫できる範囲から始めていくことが肝要です。 だからこそ、「やらなければならないから仕方なくやる」というところから抜け出し、「必要だと感じるから工夫を続ける」ところに至ることも大切だと考えています。そのために、思考停止せず、「今私たちにできること」の最大限を積み重ねていくためのお手伝いもさせていただきながら、私たち自身も含め、少しずつサステナブルな未来や世界を実現していくことができればと思っています。
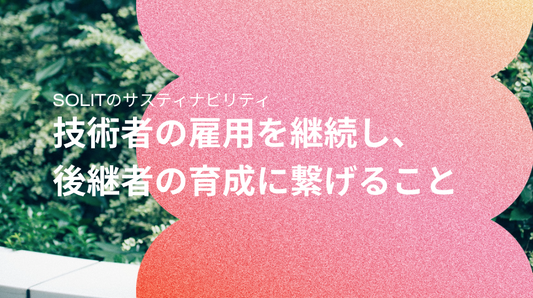
技術者の雇用を継続し、後継者の育成に繋げること
私たちPROJECT SOLITが大切にしているサスティナビリティの視点のひとつ、「技術者の雇用を継続し、後継者の育成に繋げること」についてご紹介します。 関連記事:SOLITの5つのサステナビリティ 技術者の雇用を継続し、後継者の育成に繋げること 縫製工場では、後継者を育てる環境も少なくなり、技術の継承ができなくなっていることが喫緊の課題となっています。 これまでの大量生産の方法は、効率を重視し、衣服の同じ部分を縫製し続けるライン生産方式が多くなっていたため、一人で一着全ての縫製を行う「丸縫い」をすることが少なくなっていました。一つの工程しか縫製方法を勉強できなかった方々は、一着丸々縫うことが出来ないため、本人のスキルアップやキャリアアップにも手が届きにくいという課題も生まれています。さらには「丸縫い」の技術を知る人が減っていくことで、技術が途絶えてしまうことも懸念されています。 PROJECT SOLITが作る「SOLIT!」のカスタマイズ可能な服は、「丸縫い」で縫製されるため、プロダクトを縫製することによって「丸縫い」の縫製をする機会が増えます。一人で縫いあげる「丸縫い」の仕事が安定的にあると、技術を持った人を雇用し続けることができ、さらには後継者の育成や、技術者のキャリアアップにも繋がっていくと考えています。
技術者の雇用を継続し、後継者の育成に繋げること
私たちPROJECT SOLITが大切にしているサスティナビリティの視点のひとつ、「技術者の雇用を継続し、後継者の育成に繋げること」についてご紹介します。 関連記事:SOLITの5つのサステナビリティ 技術者の雇用を継続し、後継者の育成に繋げること 縫製工場では、後継者を育てる環境も少なくなり、技術の継承ができなくなっていることが喫緊の課題となっています。 これまでの大量生産の方法は、効率を重視し、衣服の同じ部分を縫製し続けるライン生産方式が多くなっていたため、一人で一着全ての縫製を行う「丸縫い」をすることが少なくなっていました。一つの工程しか縫製方法を勉強できなかった方々は、一着丸々縫うことが出来ないため、本人のスキルアップやキャリアアップにも手が届きにくいという課題も生まれています。さらには「丸縫い」の技術を知る人が減っていくことで、技術が途絶えてしまうことも懸念されています。 PROJECT SOLITが作る「SOLIT!」のカスタマイズ可能な服は、「丸縫い」で縫製されるため、プロダクトを縫製することによって「丸縫い」の縫製をする機会が増えます。一人で縫いあげる「丸縫い」の仕事が安定的にあると、技術を持った人を雇用し続けることができ、さらには後継者の育成や、技術者のキャリアアップにも繋がっていくと考えています。

SOLITの5つのサステナビリティ
SOLITでは、指針として「5つのサステナビリティ」を掲げ、関わるすべての取り組みにおいてこれらの視点を大切にプロジェクトを進めることを決めています。 5つのサステナビリティ NO MORE WASTE / 不必要なものを生み出さない 必要とされた分だけ受注生産・小ロット生産をすることによって生産ロスを生みません。商品を購入して持ち帰れば捨ててしまうだけの下げ札や、着用に必要のないタグなどをそもそもつけていません。 関連記事:生み出し方と生み出す責任 LONG-LIFE PRODUCT / 商品寿命の長期化 一着一着、耐久性のある素材を活用することで、より長く使っていただけます。 セミオーダーで身体に合うものを選んでいただくので、購入したけれど合わなかったから廃棄する...ということを極力少なくしています。 汚れや摩耗などの際はいつでも相談をお受けし、リペア・リメイクのサポートをさせていただきます。 PROJECT AWAKE RECYCLING・REPURPOSING / リサイクルと再価値化 リサイクル段ボールでの配送をし、梱包に不必要なバージン素材や石油由来の素材を使いません。 輸送効率を高めるため、余分な空間を作らずぴったりサイズの箱または袋で配送をします。 商品の保護には、工場において未使用なのにもかかわらず廃棄となってしまう予定だった「残布」を再活用しています。 着続けていただいてもなお、それでも着なくなった服は回収し研究のために活用します。また、その上で使い果たした服はリサイクルパートナーと連携してリサイクル・循環にまわし、リサイクルや循環においてもできる限りエネルギーを使わない工夫をします。 関連記事:人と環境と共にあるための紙と印刷戦略 HUMAN RIGHTS / 人権保護...
SOLITの5つのサステナビリティ
SOLITでは、指針として「5つのサステナビリティ」を掲げ、関わるすべての取り組みにおいてこれらの視点を大切にプロジェクトを進めることを決めています。 5つのサステナビリティ NO MORE WASTE / 不必要なものを生み出さない 必要とされた分だけ受注生産・小ロット生産をすることによって生産ロスを生みません。商品を購入して持ち帰れば捨ててしまうだけの下げ札や、着用に必要のないタグなどをそもそもつけていません。 関連記事:生み出し方と生み出す責任 LONG-LIFE PRODUCT / 商品寿命の長期化 一着一着、耐久性のある素材を活用することで、より長く使っていただけます。 セミオーダーで身体に合うものを選んでいただくので、購入したけれど合わなかったから廃棄する...ということを極力少なくしています。 汚れや摩耗などの際はいつでも相談をお受けし、リペア・リメイクのサポートをさせていただきます。 PROJECT AWAKE RECYCLING・REPURPOSING / リサイクルと再価値化 リサイクル段ボールでの配送をし、梱包に不必要なバージン素材や石油由来の素材を使いません。 輸送効率を高めるため、余分な空間を作らずぴったりサイズの箱または袋で配送をします。 商品の保護には、工場において未使用なのにもかかわらず廃棄となってしまう予定だった「残布」を再活用しています。 着続けていただいてもなお、それでも着なくなった服は回収し研究のために活用します。また、その上で使い果たした服はリサイクルパートナーと連携してリサイクル・循環にまわし、リサイクルや循環においてもできる限りエネルギーを使わない工夫をします。 関連記事:人と環境と共にあるための紙と印刷戦略 HUMAN RIGHTS / 人権保護...
